足利尊氏に敗れた阿蘇惟直(あそこれなお)
私は登山に興味はないのですが、天山(1,046.2m)という山に登ったことがあります。
天山は佐賀県(肥前国)にあるのですが、なぜかその山頂には、熊本県(肥後国)の武士 阿蘇惟直(あそこれなお)の墓碑があります。
ここに本当に惟直の遺骸が葬られているかは定かではありませんが、地元には、惟直が「阿蘇の煙が見えるところに埋葬してほしい。」と言い残して自害した、という言い伝えがあります。
1336年(延元元年)2月、足利尊氏は摂津で新田義貞・北畠顕家らの軍に大敗して、九州へのがれます。
そして、同年3月、筑前の多々良浜(福岡市東区)において、尊氏方と宮方に分かれて合戦が行われました。
肥後の阿蘇氏は、同じく肥後の菊池氏とともに宮方として戦いますが、多々良浜の戦いに敗れ、敗走しました。
◎阿蘇惟直は、脊振山地を越えて肥後へ帰ろうとしますが、途中で断念し、自害しました。
*その場所については定かではありませんが、小杵山(唐津市厳木町の天川付近)或いは白坂峠(小城市と佐賀市の堺の峠)という説があるようです。
◎ところで、惟直の弟 ” 阿蘇惟成(これなり) ”も自害したとか、討ち死にしたとされていますが、佐賀市富士町の古湯温泉の近くの神社には、阿蘇惟成が住んだ九郎堂 に関する石碑があります。
◎この石碑のそばにある解説を読むと、地元には、弟の惟成が隠れ住んだという言い伝えがあるようです。
◆ 筑後川流域の歴史を研究されている方のブログ「伝説紀行 九郎堂由来 佐賀市(富士町)」が参考になります。






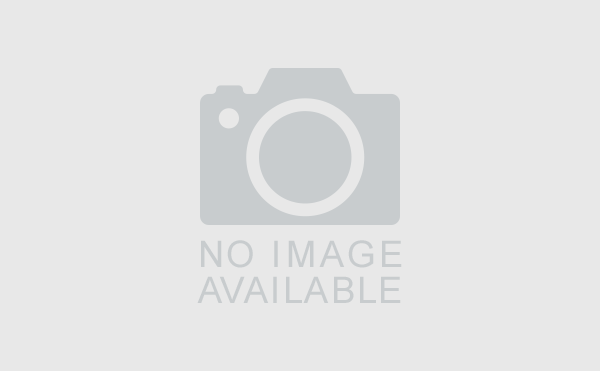
「姫御前」の記事を読み懐かしくて筆を執りました。
私は小城市栗原峯村の出身です。現在96才ですが、中学2年の14才まで村で育ちました。峰山の向かいの小山に石を積み重ねてつくられた洞がありました。洞は灌木で覆われていて村人は「姫御前さん」と呼んでいました。今でも残っているかどうか分かりませんが、小さい頃2回ぐらい洞の中に入った記憶があります。入り口は四角形で2mぐらい入ると中は円い天井になっていて小さな50cm位の碑がありました。天井は石の隙間から陽が漏れていました。入り口は何故かきらきら光って油石のようでした。向かいの山肌に塚が数基ありましたね。姫御前さんの従者の墓だと言い伝えられていましたが、小さい頃はこの付近で紅天狗茸を採っていました。毒茸ですが水にさらして食べていましたね。今はもう蜜柑畑になっているようです。手前の雑木林の中にも三根修左衛門の墓という、これも50cm足らずの墓碑がありましたが、これももう蜜柑畑になっていてます。小さい頃は向かいの山に祀られている弁天さんの祭りで、村人が鍋釜下げて食事をし子供達は藤の花の咲く林の中を走り回って戦争ごっこをしたことを想い出します。いまでも「姫御前さん」は残っているのかどうか、故郷を離れて僅か80年、滄桑の変を感じます。
コメントありがとうございます。私がホームページをほったからしていたため返信が遅れました。申し訳ありませんでした。